・契約内容のミスマッチや孤立感、待遇格差など「やめとけ」と感じる瞬間が多い
・SESはエンジニアを「商品」として扱う構造があり、案件ガチャや評価依存のリスクが大きい
・ただし案件内容やフォロー体制次第ではスキルアップやキャリアのプラスになる場合もある
・大切なのは「自分に合う働き方か」を見極め、長期的なキャリアの視点で選択すること
ITエンジニアとして働く中でよく耳にする言葉のひとつが「客先常駐はやめとけ」というものです。特にSES(システムエンジニアリングサービス)で働く人にとって、この働き方に対して不安や不満を抱えるケースは少なくありません。
なぜ客先常駐が敬遠されるのか、その理由を正しく理解しておくことは、これからエンジニアとしてキャリアを築いていく上で非常に重要です。単にネガティブな噂を鵜呑みにするのではなく、自分にとって本当に合う働き方なのかを見極める必要があります。
この記事では、客先常駐が「やめとけ」と言われる理由や具体的な瞬間、リスクやデメリット、そして向いている人の特徴や代替のキャリア選択肢までを詳しく解説していきます。最後まで読めば、自分に合う働き方の方向性がきっと見えてくるでしょう。
客先常駐はなぜ「やめとけ」と言われるのか
客先常駐という働き方には、エンジニアにとってキャリアや働きやすさに大きな影響を与える要素があります。ここでは代表的な理由を紹介します。
自社に帰属意識を持ちにくいから
客先常駐で働く場合、多くの時間を他社のオフィスで過ごすことになります。そのため、自社の同僚や文化に触れる機会が少なくなり、自分の会社に所属している感覚が薄れてしまいがちです。
ときには、自社の存在を忘れてしまうほど客先に馴染んでしまい、自分がどこの社員なのかわからなくなるケースもあります。これはモチベーション低下やキャリア不安につながりやすい要因です。
帰属意識を持てない環境は、長期的に見て働きにくさを感じる原因となりやすいのです。
この状況を回避するためには、自社が定期的にフォローをしてくれるかどうかも重要なポイントになります。
スキルアップの機会が限られるから
客先常駐では、参画するプロジェクトの内容によって得られるスキルが大きく変わります。もしルーチン作業ばかりの案件に入ってしまうと、成長の機会が非常に限られてしまうのです。
また、客先が必要とする作業だけを求められるため、自分が学びたい分野のスキルが身につかない場合もあります。これが長く続くと、キャリアの幅が狭くなり転職活動で不利になってしまいます。
常駐先の仕事がスキルアップにつながるかどうかは運要素が強いという点が問題視されるのです。
そのため、SES企業の営業や担当者がどのように案件を選んでいるかも、将来性を左右する重要な要素になります。
キャリア形成の道が見えにくいから
客先常駐の働き方では、キャリアの見通しが立ちにくいという特徴もあります。プロジェクトが終わればまた別の現場に移動するため、キャリアの一貫性を保つことが難しいのです。
結果的に「どんなエンジニアを目指しているのか」が不明確なまま年数だけが経過してしまい、転職市場でアピールしにくい経歴になってしまうこともあります。
キャリアを長期的に考える人にとって、常駐型の働き方はリスクになりやすいのです。
逆に言えば、キャリアを自分で主体的に描ける人であれば、このリスクを回避できる可能性もあります。
客先常駐で「やめとけ」と感じる具体的な瞬間
ここでは、実際に常駐先で働くエンジニアが「やめとけ」と実感する瞬間を具体的に解説します。
契約内容と実際の業務が違ったとき
SESでは「開発案件に参画できる」と聞いていたのに、実際にはテストやサポートばかりだったというケースは珍しくありません。契約段階での業務内容と現場での実務が異なることはよくあります。
特にエンジニアとして開発スキルを磨きたい人にとっては、大きな不満やキャリア停滞につながる瞬間です。
仕事内容のミスマッチは、客先常駐で最もよくある不満のひとつです。
このような状況を避けるには、事前に契約内容をしっかり確認し、担当営業に細かく質問することが大切です。
客先の社員と格差を感じたとき
同じプロジェクトで働いていても、客先社員とSESエンジニアでは待遇や評価が大きく異なる場合があります。昇進や研修機会は客先社員だけに与えられる一方、SESエンジニアにはチャンスがないことも多いです。
また、重要な意思決定や会議に参加できないなど、立場の違いがはっきり表れる瞬間もあります。
「同じように働いているのに待遇が違う」という格差は、大きなストレス源になります。
これは多くのエンジニアが客先常駐を敬遠する理由のひとつです。
会社からのフォローがなく孤立したとき
客先常駐では、日常的に自社との接点がほとんどありません。そのため、困ったときに相談できる相手がいないまま孤立してしまう人も多いです。
ときには「自分は本当にこの会社の社員なのか?」と不安になるほどサポートが不足している企業も存在します。
孤立感が強まると、メンタル不調や離職につながるリスクが高まります。
フォロー体制のあるSES企業かどうかを見極めることは非常に重要です。
常駐先のプロジェクトが突然終了したとき
プロジェクトの事情で急に契約が終了し、次の案件が決まるまで待機状態になることもあります。このようなケースでは収入やキャリアが不安定になりやすいです。
特に待機期間が長引けば、会社への不信感や焦りが強くなります。
プロジェクト終了が自分の意思とは関係なく訪れるのも、常駐型ならではの不安定さです。
安定を求める人にとっては、このリスクが「やめとけ」と感じる大きな要因になります。
SESの働き方で客先常駐が「やめとけ」とされる理由
SESの仕組みそのものが、エンジニアにとって不利に働く要素を含んでいます。ここではその根本的な理由を解説します。
エンジニアが「商品」のように扱われるから
SESでは、エンジニアのスキルや経験が「時間単価」として取引されます。この仕組みは、エンジニア個人の成長や希望よりも、顧客のニーズが優先される構造です。
結果として、自分がやりたい仕事ではなく「売れるスキル」によって案件が決まることが多くなります。
エンジニアが主体的にキャリアを選びにくいのは、SESの構造上の大きな欠点です。
この点を理解せずにSES業界に入ると、思い描いていたキャリアとのギャップに悩むことになります。
評価が常駐先に依存してしまうから
常駐先での業務評価が、そのまま自社での評価につながることがあります。つまり、SES企業の上司が直接仕事ぶりを見るわけではなく、客先の評価に左右されやすいのです。
これは、自分の実力とは関係のない要素で評価が決まるリスクを含んでいます。たとえば、プロジェクトの雰囲気や上司との相性によって評価が変わってしまうこともあります。
自分の努力が正しく評価されにくいのは、SES特有の不満ポイントです。
評価制度が透明でないSES企業ほど、この問題は深刻になります。
案件ガチャで運任せのキャリアになりやすいから
SESでは、配属される案件が自分で選べないケースが多くあります。スキルアップにつながる案件に当たることもあれば、逆に成長につながらない案件を任されることもあります。
この「案件ガチャ」状態は、長期的なキャリア形成にとって大きなリスクです。
自分のキャリアが会社の営業次第で決まってしまうのは、エンジニアとして大きな不安要素です。
そのため、案件選択にどこまで裁量を持たせてくれるSES企業かを確認することが重要です。
長期的にスキルが固定されやすいから
一度ある案件に入ってしまうと、数年単位で同じ業務を続けることになる場合があります。そうすると、特定のスキルだけが固定化され、新しい技術に触れる機会を失いやすいです。
IT業界は技術の進歩が早いため、学び続けなければスキルが陳腐化してしまいます。常駐型の働き方では、そのリスクが顕著に表れます。
長期的に見て市場価値を落とす危険性があることが、SESの最大のデメリットです。
この問題を避けるには、自分で学習を続けたり副業で経験を積むなどの工夫が必要です。
客先常駐を続けると「やめとけ」と思うリスクやデメリット
長期間客先常駐を続けると、キャリアや生活に具体的な悪影響が出てきます。
スキルが限定され転職に不利になる
常駐先の業務が限られている場合、そのスキルしか習得できず転職市場で評価されにくくなります。幅広い経験を積みたい人にとっては、大きなハンデになります。
また「何ができるエンジニアなのか」を明確にアピールできないことが、選考で不利に働きやすいです。
スキルの幅が広がらないことは、転職の可能性を狭めてしまうリスクがあります。
そのため、キャリアの停滞を避けたいなら自発的な学習が欠かせません。
単価が上がりにくく年収が伸びにくい
SESではエンジニアの単価が会社と顧客の契約で決まるため、自分のスキルが直接年収に反映されにくい仕組みになっています。
さらに、会社が中間マージンを取るため、エンジニアが受け取る報酬は限られてしまいます。どれだけ努力しても年収が大きく伸びにくい構造なのです。
「働いた分だけ評価されたい」と考える人には、SESの報酬体系は不満が残りやすいです。
これが原因で、より待遇の良いフリーランスや自社開発への転職を考える人も多いです。
メンタル不調や燃え尽きにつながるリスク
客先常駐では、孤独感や不安定さから精神的に疲れてしまう人もいます。特に自社のサポートがない企業に所属している場合、メンタル不調に陥りやすいです。
また、仕事内容に不満を抱えながら働き続けることで、やる気を失って燃え尽きてしまうケースもあります。
環境によるストレスが積み重なり、心身に悪影響を及ぼすのは大きなリスクです。
働き方を選ぶ際には、精神面での負担がどうかを考えることも大切です。
正社員なのにプロジェクト終了で待機になる可能性
SES企業の社員であっても、プロジェクトが終われば待機状態になることがあります。これは収入や評価に直結するため、安心して働ける環境とは言いにくいです。
待機期間が長引けば、給与の減額や解雇リスクにつながる可能性もゼロではありません。
「正社員なのに安定していない」という矛盾が、SESの働き方の大きな欠点です。
安定志向の人にとっては、客先常駐は避けたほうが良い選択になるでしょう。
客先常駐でも「やめとけ」とは限らないケースとは
ただし、すべての客先常駐が悪いわけではありません。条件次第では、プラスに働くケースも存在します。
大手企業の長期プロジェクトに参画できる場合
大手企業の大規模なプロジェクトに長期で参画できる場合、安定感があり最新の技術に触れるチャンスも得られます。
特に大企業の開発環境は整っているため、学びやすい環境で経験を積むことが可能です。
案件によってはキャリアの大きなプラスになることもあります。
そのため、常駐先の規模や環境を見極めることが重要です。
常駐先で直接雇用のチャンスがある場合
常駐先での働きぶりが評価され、直接雇用のオファーをもらえることもあります。これはキャリアアップの大きなチャンスになります。
特に自社より待遇が良い企業に転職できれば、収入やスキルの面でプラスになります。
客先常駐をきっかけにキャリアを広げられる可能性もあるのです。
このようなチャンスを活かせる人は、常駐型を前向きに捉えることができます。
スキルアップに直結する案件に参画できる場合
もし参画した案件が最新技術を扱う内容であれば、大きなスキルアップが期待できます。たとえばクラウドやAIなど成長分野の案件は市場価値を高める武器になります。
案件選びさえ適切であれば、客先常駐は効率よくスキルを伸ばす手段になり得ます。
「どんな案件に参画できるか」が鍵となるのです。
事前に案件内容を確認することが欠かせません。
フォロー体制の整ったSES企業に所属している場合
定期的に面談やサポートがあり、キャリア相談ができるSES企業も存在します。このような会社であれば、客先常駐でも安心して働けます。
また、待機期間の給与保証や研修制度がある企業なら、スキルアップと安定を両立できます。
SES企業のサポート体制が整っていれば「やめとけ」とは限らないのです。
会社選びの段階で、フォロー体制を確認することが成功の鍵です。
客先常駐が「やめとけ」と言われるけど向いている人の特徴
すべての人にとって客先常駐が悪いわけではありません。向いている人もいます。
環境の変化に柔軟に対応できる人
常駐先は数年ごとに変わることが多いため、新しい環境に順応できる柔軟性が求められます。
変化を楽しめる人にとっては、客先常駐はむしろ刺激的な働き方です。
柔軟さを持つ人は客先常駐を活かせます。
一方、安定を強く求める人には不向きです。
人間関係を築くのが得意な人
常駐先では新しい人との出会いが多いため、コミュニケーション能力が重要です。人間関係を築くのが得意な人は、どんな現場でも評価されやすいです。
新しい職場に馴染む力は、客先常駐で強みになります。
人付き合いが得意なら、常駐型でもストレスを減らせます。
逆に人間関係に不安を感じる人には負担が大きいでしょう。
自分で学習を継続できる人
常駐先ではスキルアップの機会が限られるため、自学自習が欠かせません。自主的に学習を続けられる人なら、キャリア停滞を防げます。
資格取得や個人開発などを通じて、自分の市場価値を高めていける人が向いています。
自分で学び続けられる人は、SESの弱点をカバーできます。
逆に受け身の姿勢だとキャリアが停滞してしまいます。
安定より経験を優先する人
「とにかくいろいろな現場で経験を積みたい」という人にとっては、常駐型は有利です。多様な業界や環境を経験できるため、視野を広げられます。
キャリアの初期に幅広い経験を積む手段としては有効です。
安定より経験を重視する人にとって、常駐はチャンスの多い働き方です。
ただし長期的には安定性を求めた転職を検討する必要が出てきます。
客先常駐を選ばず「やめとけ」と言われない働き方の選択肢
もし客先常駐を避けたいなら、他にもキャリアの選択肢はあります。
自社開発企業で働く
自社開発では、自社のサービスや製品に携わり、長期的にスキルを磨くことができます。安定した環境でキャリアを築きやすいのが魅力です。
腰を据えて成長したい人には、自社開発企業がおすすめです。
ただし採用倍率が高いので、スキルを磨いて挑戦する必要があります。
受託開発企業で案件に関わる
受託開発では、複数のクライアント案件に関われます。客先常駐よりも自社オフィスで働く機会が多いのが特徴です。
幅広い業務経験を積みながら、自社に所属している感覚を持てます。
安定と多様性のバランスを求める人に適しています。
フリーランスエンジニアになる
フリーランスなら案件を自分で選べるため、やりたい仕事やスキルを重視できます。報酬もSESより高くなることが多いです。
自由度の高さと高収入が魅力ですが、自己管理能力が求められます。
独立を目指す人には挑戦する価値があります。
リモートワーク可能なIT企業に転職する
リモートワークを導入している企業に転職すれば、客先常駐のように場所に縛られることがありません。ワークライフバランスを重視する人に人気の選択肢です。
働く場所を自由に選べるのは大きなメリットです。
ただし自己管理能力や成果主義に対応する力が必要になります。
まとめ|客先常駐を「やめとけ」と感じる前に知っておきたいこと
ここまで解説してきたように、客先常駐にはリスクやデメリットが多く存在します。しかし条件次第ではキャリアのプラスになるケースもあります。
なぜ「やめとけ」と言われるのかを理解する
客先常駐は帰属意識が薄れやすく、スキルやキャリア形成に不利になる可能性があります。その理由を理解した上で選ぶことが大切です。
盲目的に避けるのではなく、リスクを理解して判断しましょう。
情報不足のまま就職すると後悔しやすいので注意が必要です。
自分に合う働き方を見極めることが大切
客先常駐が合わない人もいれば、向いている人もいます。自分の性格やキャリアプランに合うかどうかをしっかり見極めることが必要です。
他人の意見ではなく、自分の軸で選ぶことが成功への近道です。
合わないと感じたら、早めに別の選択肢を探すのも賢い方法です。
キャリアを長期的に考えて選択する
エンジニアのキャリアは数年先を見据えて選択することが重要です。目先の収入や環境だけでなく、将来的に市場価値が高まるかを基準に判断しましょう。
長期的な視点を持つことで、後悔のないキャリア形成が可能になります。
「やめとけ」と言われる働き方でも、自分にとってプラスになるなら選択肢のひとつとして考えて良いのです。
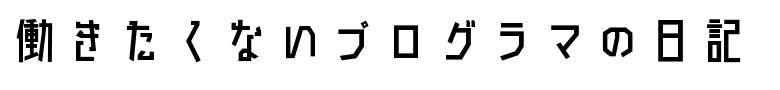




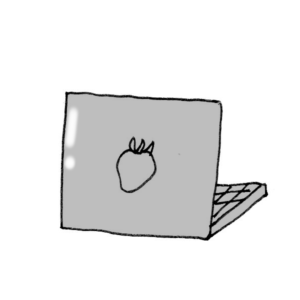
コメントを残す