・就職市場では未経験歓迎求人が減り、初級ポジションの倍率が高騰している
・採用される人はポートフォリオやGitHub公開、チーム開発経験など実務に近い経験を示している
・必要なのはWebアプリ開発やクラウド基盤、Git・Dockerなどの実践的スキルに加えて継続的な学習姿勢
・業界全体では教育コストや離職率の増加といった課題があるが、差別化できる人材には十分なチャンスがある
近年、プログラミングスクールやリスキリング支援の拡大によって、未経験からエンジニアを目指す人が急増しています。しかし「未経験エンジニアが増えすぎた」と言われる現状には、就職市場の変化や採用のハードルの上昇といった厳しい現実があります。本記事では、なぜ未経験エンジニアが増えているのか、その背景と就職市場で起きている変化、採用される人の特徴、そして今後必要なスキルや課題について詳しく解説します。未経験からエンジニアを目指す方にとって、これからのキャリア戦略を考える参考になるでしょう。
なぜ未経験エンジニアが増えすぎと言われるのか
未経験エンジニアが急増していると言われるのは、求人市場における供給と需要のバランスが崩れているからです。ここではその具体的な理由を解説します。
プログラミングスクール卒業生が急増しているから
ここ数年でプログラミングスクールが全国的に増加し、数万人規模で卒業生が誕生しています。スクールは短期間でスキルを習得できると宣伝しており、多くの社会人や学生が新しいキャリアを求めて受講しています。
しかし、スクールで学べるのは基礎的な内容が中心であり、実務経験と比べると差が大きいのが現実です。卒業生が同じタイミングで就職活動を行うことで、求人の競争率が急激に高まっているのです。
結果として「スクール卒業=すぐに就職できる」という時代は終わり、差別化がますます重要になっています。
採用する企業側も「スクール卒業生が増えすぎた」と感じるほど、応募数の増加を実感しています。
求人倍率が低下しているから
以前はIT業界の求人倍率は非常に高く、1人の求職者に対して複数の企業が競う状況でした。しかし、ここ数年で求人倍率は下がりつつあります。
特に未経験エンジニア向けのポジションは応募者が集中しやすく、倍率が一気に跳ね上がる傾向があります。そのため「未経験枠」に挑戦しても、なかなか内定が得られない人が増えています。
求人の絶対数が増えていても、求職者の方がそれ以上に増えているため、結果的にチャンスが減っているのです。
こうした状況が「未経験エンジニアが増えすぎた」と言われる要因の一つになっています。
経験者優遇の採用が増えているから
企業は即戦力を求める傾向が強まっています。IT業界のプロジェクトは納期や品質が厳しく、教育コストをかけて未経験者を育てる余裕が少ないからです。
そのため、同じ求人でも「経験者歓迎」「経験者優遇」といった文言が増え、未経験者が応募しても通過が難しくなっています。
結果として、未経験者の母数が増える一方で、採用枠は狭まっているというギャップが生まれているのです。
この傾向は今後も続くと予想され、未経験エンジニアが就職するにはさらなる工夫が必要になっています。
未経験エンジニアが増えすぎている背景とは
ではなぜ、ここまで未経験エンジニアが急増したのでしょうか。その背景には社会的な変化や教育ビジネスの拡大があります。
リモートワーク人気でIT職種に注目が集まったから
コロナ禍をきっかけにリモートワークが広まりました。その中で、場所を選ばず働けるITエンジニアという職種に注目が集まったのです。
営業や接客といった職種から転職を希望する人も増え、ライフスタイルの変化に合わせてキャリアを選ぶ動きが強まりました。
「在宅で働ける」「自由な働き方ができる」という魅力が、未経験者の参入を後押ししたと言えるでしょう。
この流れは今も続いており、IT業界の人気は高止まりしています。
テックキャンプやDMM WEBCAMPなど大手スクールの広告が拡大したから
テレビCMやSNS広告で、プログラミングスクールの宣伝を目にする機会が増えました。「未経験からでもエンジニアになれる」というメッセージは、多くの人の心を動かしました。
テックキャンプ、DMM WEBCAMP、TECH I.S.など、大手スクールは大規模な広告投資を行い、受講者数を拡大しています。
結果として、エンジニア転職が「特別な人だけのものではなく、誰でも挑戦できるもの」と認識されるようになったのです。
ただし、広告の印象と実際の就職難易度には差があり、ギャップを感じる人も少なくありません。
政府のリスキリング支援でIT転職が推進されたから
政府はデジタル人材の不足を解消するため、リスキリング支援を強化しています。補助金や職業訓練を通じて、多くの社会人がITスキルを学ぶ機会を得ました。
また「2025年の崖」と呼ばれるシステム更新問題を背景に、国全体でIT人材の育成が重要視されています。
こうした政策が後押しとなり、異業種からIT業界へ挑戦する人が増えたのです。
社会的な流れそのものが、未経験エンジニア急増の原因になっています。
未経験エンジニアが増えすぎたことで就職市場に起きている変化
未経験者が急増したことで、就職市場にはいくつかの大きな変化が現れています。
初級エンジニア求人の倍率が高騰している
「未経験OK」や「第二新卒歓迎」といった初級エンジニア向けの求人は、応募が殺到するようになりました。倍率が10倍以上になることも珍しくありません。
その結果、内定を得るのは一部の準備ができた人に限られ、多くの人が選考に落ち続ける現状があります。
求人自体はあるが、倍率が上がりすぎて未経験者にとっては狭き門になっているのです。
採用されるには工夫と実力のアピールが必要不可欠になっています。
未経験歓迎求人が減少している
数年前までは「未経験歓迎」の求人が豊富にありました。しかし、未経験者の応募が集中しすぎたことで、企業側は選考基準を引き上げています。
現在は「未経験歓迎」と書かれていても、実際には何らかの学習経験やポートフォリオ提出を求められるケースが多いです。
未経験者が増えすぎたことで、求人票の条件が実質的に「経験者優遇」に近づいているとも言えます。
そのため「とりあえず応募してみよう」という姿勢では通用しにくくなっています。
SES企業や受託企業への就職が中心になっている
大手企業や自社開発企業の門戸は狭く、未経験者が直接入社するのは難しくなっています。そのため、多くの人が最初のキャリアとしてSES企業や受託開発企業を選ぶケースが増えました。
これらの企業では教育体制が整っている場合もありますが、プロジェクトによっては単純作業に配属されることもあります。
未経験者が最初に入れる企業の選択肢が偏っていることが、就職市場の特徴となっています。
キャリアを積むためには、入社後の努力が非常に大切です。
未経験エンジニアが増えすぎても採用される人の特徴
未経験エンジニアが急増する中で、それでも採用される人には共通する特徴があります。ここでは特に重要なポイントを整理します。
ポートフォリオで実務に近い開発経験を示せる人
採用担当者が注目するのは、実際にどのようなプロダクトを作ったかです。スクールの課題だけでなく、自分で考えて作ったWebサービスやアプリをポートフォリオに載せると高く評価されます。
「どの技術を使ったか」だけでなく「どんな課題を解決するために作ったのか」を明確に説明できると効果的です。
例えば、タスク管理アプリやブログシステムなどでも、独自機能を実装することで差別化できます。
採用担当者は「この人が入社したらどんな貢献ができるか」をポートフォリオから判断するため、完成度が重要になります。
GitHubでコードを公開している人
GitHubにコードを公開している人は、学習の継続性や技術力をアピールできます。コードの質やコミットの頻度を見るだけでも、その人の学習姿勢が伝わります。
採用担当者にとって、言葉よりもコードそのものが最大の証拠です。日々の学習を積み重ねて公開しておけば、ポートフォリオと合わせて強力な武器になります。
また、オープンソースへの貢献や他人のリポジトリへの参加経験があると、チーム開発力も評価されやすいです。
「コードを見せられるかどうか」が、未経験者の差別化ポイントになっています。
チーム開発経験(スクールやハッカソン)がある人
エンジニアの仕事は個人作業だけではなく、チームで協力して進めることが多いです。そのため、チーム開発の経験がある人は採用で有利になります。
プログラミングスクールの中にはチーム開発課題を取り入れているところもあり、ハッカソンに参加する人もいます。
チームでGitを使って開発した経験や、役割分担をして完成させた経験は大きな強みです。
面接では「どのような役割を担当したのか」「どんな課題をどう解決したのか」を話せるとさらに効果的です。
長期的に学習を継続している人
採用担当者は「この人は入社後も学び続けられるか」を見ています。短期間だけ勉強した人と、半年〜1年以上継続して学んでいる人では印象が大きく違います。
ブログやSNSで学習の記録を発信するのも有効です。特に毎日の積み重ねが見える形で残っていると、継続力の証明になります。
IT業界は常に技術が進化するため、継続的に学習する姿勢が最も重要と言えます。
「学び続ける人材」であることを示すことが、未経験者にとって最大の武器です。
未経験エンジニアが増えすぎた現状で必要なスキルとは
未経験者が多い中で、採用されるには「即戦力に近いスキル」を持っていることが重要です。具体的にどのようなスキルが求められているのかを見ていきましょう。
Webアプリ開発スキル(React、Next.js、Laravelなど)
企業が最も求めているのはWebアプリの開発スキルです。フロントエンドではReactやNext.js、バックエンドではLaravelやRuby on Railsがよく使われています。
これらの技術でポートフォリオを作れば、実務に近い経験をアピールできます。
「どのフレームワークを学んだか」だけでなく「それを使って何を作ったか」が重要です。
Webアプリ開発のスキルは未経験者にとって必須と言えるでしょう。
クラウド基盤の理解(AWSやGCPの基礎)
近年は多くの企業がクラウド環境を利用しています。AWSやGCPの基礎を理解していると評価が高まります。
EC2やS3などの基本的なサービスを使った経験を持っていると、ポートフォリオの説得力が上がります。
クラウドの知識は実務で必須になりつつあり、未経験者が差をつける大きなポイントです。
最低限、インフラの基礎を学んでおくことをおすすめします。
Git・Dockerなどの開発環境スキル
チーム開発ではGitでのバージョン管理は必須です。さらにDockerで環境を構築できると実務に近いスキルとして評価されます。
GitHubを使った共同開発経験や、Dockerを使ったローカル環境構築を経験していると、選考で有利に働きます。
「環境構築ができる人」は現場で即戦力として期待されやすいのです。
学習段階から開発環境スキルを取り入れておくことが重要です。
コミュニケーションスキルや業務理解力
エンジニアには技術だけでなく、チームで協力して進める力も求められます。特に未経験者の場合、技術で差をつけにくいため、コミュニケーション力が大きな評価ポイントになります。
業務理解力、つまり「なぜそのシステムを作るのか」を理解する姿勢も重要です。
技術だけでなく、チームワークや業務理解を含めて成長できる人材が採用されやすいのです。
面接では技術だけでなく、協働の経験や学びの姿勢もアピールしましょう。
未経験エンジニアが増えすぎた中での転職活動のポイント
未経験エンジニアが就職するためには、工夫が欠かせません。ここでは実際の転職活動で意識すべきポイントを解説します。
ポートフォリオサイトを充実させる
ポートフォリオは未経験者にとって最大の武器です。作品をまとめて見せることで、実力を客観的に伝えられます。
ただアプリを作るだけでなく、設計図や使用技術、工夫したポイントを説明できるとより説得力が増します。
採用担当者が「この人は本当に手を動かしている」と感じられるポートフォリオを用意することが重要です。
自作サイトとして公開することで、技術力と実践力の両方をアピールできます。
WantedlyやGreenなどIT転職特化サイトを活用する
一般的な転職サイトよりも、IT業界に特化したサービスを利用する方が効率的です。WantedlyやGreenはIT企業の求人が豊富で、企業と直接やり取りできる仕組みがあります。
「応募する」だけでなく「スカウトされる」可能性もあるため、プロフィールを充実させることが大切です。
SNS感覚で企業と繋がれるため、未経験者でもチャンスを掴みやすい特徴があります。
複数の転職サイトを組み合わせて利用するのが効果的です。
未経験OKでも研修制度が整った企業を狙う
求人票に「未経験歓迎」と書かれていても、実際には教育制度が不十分なケースもあります。そのため、研修制度が整っている企業を見極めることが重要です。
社員の声や企業のブログ、採用ページを調べると研修の実態が分かることがあります。
「入社後に育成してもらえるかどうか」がキャリアの成否を分けるため、情報収集を怠らないようにしましょう。
入社後の成長を考えた企業選びがポイントです。
エージェント(レバテックキャリア、マイナビIT AGENTなど)を利用する
転職エージェントを利用すると、非公開求人や未経験向けの特別枠を紹介してもらえることがあります。特にレバテックキャリアやマイナビIT AGENTはITに強みがあります。
エージェントは面接対策や書類添削もしてくれるため、選考通過率を高められます。
自分一人で探すよりも、専門家のサポートを受ける方が効率的です。
複数のエージェントを活用して比較検討するのがおすすめです。
未経験エンジニアが増えすぎることによる業界の課題
未経験者の増加は業界全体にも影響を与えています。ここではその課題について整理します。
短期離職するエンジニアが増えている
スクール卒業後に入社しても、実際の業務とのギャップに耐えられず短期間で辞めてしまう人が増えています。
「思っていた仕事と違う」「ついていけない」という理由での離職は、業界全体の定着率を下げる原因になっています。
企業にとっても人材の流動が激しいことは課題です。
キャリア選択の時点で、現実を理解しておくことが必要です。
教育コストの増加で企業負担が大きい
未経験者を採用すると、教育に多くの時間とコストがかかります。すぐに戦力化できないため、企業側の負担が増大しています。
結果として「経験者を優先する」流れが強まり、未経験者には不利な状況になりやすいのです。
教育コストが採用のハードルを上げているのが現状です。
そのため、入社前にある程度の実力を示せる人が求められています。
スキル不足によるプロジェクト遅延リスク
未経験者が大量に配属されると、プロジェクトの進行が遅れるリスクが高まります。特に基礎が不十分な場合、現場でのトラブルに繋がりやすいです。
その結果、現場の経験者に負担が集中するケースもあります。
スキル不足が原因でプロジェクト全体に悪影響を与える可能性があるため、採用側は慎重にならざるを得ません。
この点も未経験者にとって就職が難しくなっている理由です。
経験者と未経験者の給与格差が拡大している
需要の高い経験者の給与は上昇している一方、未経験者の初任給は大きく上がっていません。そのため、給与格差が拡大しています。
特に即戦力として転職する中堅エンジニアは高年収を得やすく、未経験者との差は歴然としています。
未経験エンジニアが増えすぎた結果、競争が激化し、待遇にも影響を与えているのです。
この格差は今後も広がる可能性があります。
まとめ:未経験エンジニア増えすぎの背景と就職市場の現実
未経験エンジニアが増えすぎている背景には、リモートワークの普及、スクールの広告拡大、政府のリスキリング支援といった社会的な要因があります。その結果、初級求人の倍率は高騰し、未経験歓迎求人は減少しつつあります。
しかし、ポートフォリオやGitHub公開、チーム開発経験、長期的な学習継続といった要素を持つ人は、未経験でも採用される可能性が高まります。
今後は「ただ学んだ」だけではなく「実務に近い経験を示せるか」「学び続けられる人材か」が採用の分かれ目になるでしょう。
業界全体では教育コストや離職率といった課題もありますが、しっかり準備した人にはチャンスがあります。未経験者にとって大切なのは、現実を理解した上で、計画的にキャリアを積むことです。
「未経験エンジニア増えすぎ」の時代だからこそ、差別化を意識して行動することが成功の鍵となります。
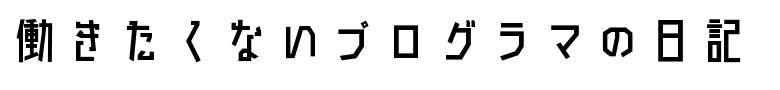








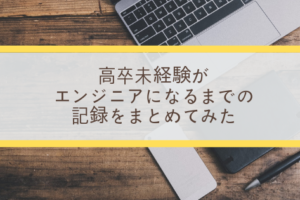



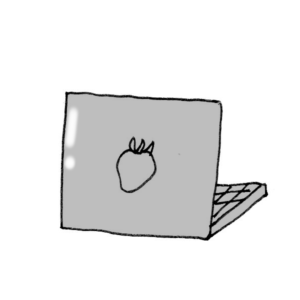
コメントを残す